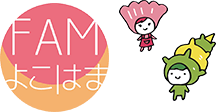2017年7月10日
こんにちは。FAM(ファム)よこはまアフタースクール開設準備室です。
私たちは、大切なお子様の命をお預かりします。
そのため、ヒトの体と心の健康についても、常日頃から勉強し、
子ども達や保護者の皆様にお伝えしていきます。
先日、宇津見眼科医院院長 宇津見義一先生による、
「子どもの目とメディアそして注意すべき目の病気」
(心因性視力障害、感染性疾患、色覚異常など)
の講演を受講しました。
講演内容は多岐にわたりましたが、特に興味深く伺ったお話は
以下の項目です。
◇IT関係のメディア〔ゲーム(TV・携帯用)、インターネット、スマートフォン〕
の利用に伴う、視力への影響
◇10代のスマートフォン利用率・利用時間
◇近視・遠視の仕組み
◇近視が進む要因、進行の予防法
◇コンタクトレンズの注意点、カラーコンタクトの問題点
(小・中・高校生の装用率)
◇ネット依存とその対応(予防教育)
◇心因性視覚障害
一つ一つについてもう少し共有できればと考えておりますが、
今回は、近視研究会による『学童の近視進行予防7項目』を
ご紹介いたします。
1.一日にできれば、2時間は外で遊ぶようにしましょう。
2.学校の休み時間は、できるだけ外で遊びましょう。
3.本は目から30㎝以上離して読みましょう。
4.読書は背を伸ばし、良い姿勢で読みましょう。
5.読書・スマホ・ゲームなどの近業は、
1時間したら5分~10分程度は休み、できるだけ外の景色を
見たり、外に出てリフレッシュしましょう。
6.規則正しい生活(早寝早起き)を心がけましょう。
7.定期的な眼科専門医の診察を受けましょう。
既に日常でされていること、知識として備わっていることも
たくさんあるかと思いますが、改めて聞くことでより生活に
反映されやすくなるのではと思います。
宇津見先生が仰っていましたが、低年齢からの習慣づけが
目の健康やメディアとの関わり方についても、大変重要とのことでした。
習慣として行ってきた時間が長いほど、その行動が持続する
傾向にあるというのは、経験的にも頷けるかと思います。
しかし、それを『習慣づけること』はとても大変です。
両親がお仕事をされている、されていないに関わらず、子どもも
大人もやるべきことが日々膨大にあり、目の前のことをしている
うちに一日が、一週間が、あっという間に終わります。
私たち学童の役割は、ここにもあると考えています。
子ども達は、幼稚園や保育園で、ルール、マナー、健康的な
生活習慣などをしっかり学びます。
せっかく身に着けてきたこの大切な習慣ですが、小学生になって
あとは自分でやってね、というのはとても難しいことです。
FAMよこはま学童クラブ(※)では、お子様方が身に着けてきた
生活習慣がそのまま続けていけるように、より健康な心身が
育まれるように、”保育”の面も充実させていきたいと
考えています。
長文お読みいただき、ありがとうございました。
※FAMGer(ファムゲル)よこはまアフタースクールと名称選考中です。