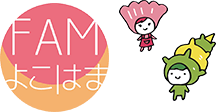2017年7月11日
こんにちは。FAM(ファム)よこはまアフタースクール開設準備室です。
前回の続きです。宇津見眼科医院院長 宇津見義一先生による
講演内容について、前回と重複しますが、特に興味深かった内容は以下のとおりです。
1.IT関係のメディア〔ゲーム(TV・携帯用)、インターネット、スマートフォン〕
の利用に伴う、視力への影響
2.10代のスマートフォン利用率・利用時間
3.近視・遠視の仕組み
4.近視が進む要因、進行の予防法
5.コンタクトレンズの注意点、カラーコンタクトの問題点
(小・中・高校生の装用率)
6.ネット依存とその対応(予防教育)
7.心因性視覚障害
本日は、データをご確認いただきたいので、1についてのみ
共有いたします。
1.IT関係のメディアの利用に伴う、視力への影響
平成16年、今から10年以上も前に日本小児科医会から
『メディアとの長時間に及ぶ接触は、心身の発達過程にある
子どもへの影響が懸念される』と警鐘が鳴らされました。
文部科学省調査の裸眼視力1.0未満の過去35年間の
データは以下のとおりです。(抜粋)
昭和55年(調査開始時) 平成16年 平成27年
高校生 55.5% 59.3% 63.8%
中学生 38.1% 47.7% 54.1%
小学生 19.7% 25.6% 31.0%
幼児 19.8% 20.8% 26.8%
その年により上がり下がりはありましたが、
いずれの年代でも、1.0未満の割合が増加しています。
また、昭和54年と平成27年度の裸眼視力0.3未満の
データはこちらです。
昭和54年 平成27年
高校生 26.29% 36.16% ☜約1.4倍増加
中学生 13.16% 25.31% ☜約1.9倍増加
小学生 2.67% 8.32% ☜約3.1倍増加
幼児 0.35% 0.7% ☜約2倍増加
世界的にも近視は増加しているようです。
ブライアン・ホールデンの視覚研究所によりますと、
◆国内総生産(GDP)の大きな国々は
近視の割合が高い傾向にある
◆社会的経済的地位が高い人々は屋外で過ごす時間が
少ないことが起因している
と論じています。
また、イアン・モーガン(オーストラリア国立大学)は
近視はほとんど遺伝だと信じられていた。
しかし、実際は社会的要因による疾患である。と論じ、
3年間にわたり、毎日40分間多く屋外過ごした子供は
対照群よりも近視になりにくかったとのデータを示しています。
近視の割合が高くなっている要因は、IT関連のメディアのみに
起因しているわけではないと思いますし、IT関連のメディアは
私たちの生活の利便性に大きく貢献していることも事実として
あります。
今後ますます利用が増えるであろうと予測もつきます。
宇津見先生も仰っていましたが、大切なことは、メディアとの
上手なつきあい方と、目や視力についての正しい知識を持つこと
ではないでしょうか。
目の成長は、6歳から8歳までの間でほぼ完成するようです。
小さい子供の視力検査は、特に3歳~4歳の年齢にとっては
とても難しく、時間もかかります。
ですが、少しでも「検査が難しいな」「見えていないのかな」
と感じられたら、小児眼科の専門医にご相談してみることで、
もしも治療が必要であれば、ピントの調節障害等であれば改善する
可能性もあるとのことですし、治療の必要が無いということで
あればひと安心できますし、やはり専門家の力を借りることは
必要だと、私自身説明を聞いて感じました。
本日も長文になりまして恐縮です。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。